
理学療法士 × 鍼灸師 × アスレティックトレーナー の鈴木 勇祐です.
解剖学や運動学,生理学を基に医学,スポーツ科学の観点からスポーツに関する情報を解き明かします.
今回はスポーツが上達するには何が必要かを記事にします.
それぞれのスポーツについては,別で記事にしますのでそちらも参考に.
スポーツの上達とは,【運動における技術の上達】とします.
ですので,走るのが速くなるとかジャンプ力についてはまた別の記事とします.
ただし,走ることもジャンプすることも【技術】が関与しますので,無関係ではありません.
まず運動時の脳内の働きを少しだけ解説していきましょう.
身体を動かす時,頭のなかでは何が起こっているか!?
スポーツが上達するとは,‘身体を思い通りに’,‘自分のイメージ通りに’動けるようになるという事です.
そのためには,どういう順序のもと身体が動いているかを知る必要があります.

身体を動かすとき,まず脳内で身体を動かすプログラミングが行われます.
このプログラムが正確かどうかがまず運動のパフォーマンスに影響します.
そのプログラム通りに電気信号が神経を伝い,筋肉に到達することで身体が動きます.
このとき,実際“身体が動いた”という感覚が脳内に戻る事を【フィードバック】(赤矢印)と言います.
これは非常に重要な事柄です.
運動をイメージする事と運動のプログラミングはほぼ同じ
スポーツ場面におけるボールの投げ方やボールキック,ゴルフスイングをイメージしてみましょう.
この【イメージしている時】も,運動している時とほぼ同じプログラミングが脳内で起こります.



キレイなボールの投げ方や蹴り方,ゴルフスイングはほとんどの人がイメージ出来ると思います.
しかし,みんなが同じようなキレイなフォームという事はありません.
つまり理想のフォームはイメージ出来ても,その通りに身体が動いていないという事です.
ここで一つ問題があります.
イメージ出来ないものはどうしたら良いでしょう?
イメージ出来ない動きは,実際に動きません.
まずイメージを構築することから始めなければなりません.
これは上達というより始めるという事になります.
イメージ出来ない事は,まず見てイメージ出来るように【動き】を覚える必要があります.


サッカーをあまり知らない人は「ラボーナをやって」と言われてもまず出来ません.
ダンスをしない人にウィンドミルなどのパワームーブはもちろん,ランニングマンなどの動きも出来ないでしょう.
まず動きを知らない事には出来ないからです.
『この動きをしたい』と思ったらまず観察しましょう.
そして頭の中で自分がそのように動くイメージをします.
イメージ出来なければその動きを実現するのは難しいので,しっかり観察し直すか実際に動いてみてイメージとの擦り合わせをしましょう。
この’イメージの摺合せ’も一つの【フィードバック】になります.

ここからは,動きをある程度イメージ出来るようになってからの解説です.
ほとんどの人は,【キレイなフォーム】がイメージ出来ます.
ボールを上手に投げられない人を思い浮かべてください.
両手投げになってしまったり,手と脚の動きがバラバラになってしまいます.
ではその人が持っている【ボールを投げるイメージ】は果たしてその通りでしょうか??
ボールを上手に投げられない人でも,ほとんどの人はプロ野球のピッチャーが投げるようなキレイなフォームがイメージ出来るはずです.
という事はその動作の良いフォームは知っているけど,思い通りに動かせていない事が原因でパフォーマンスが向上していないのであれば,イメージ通りに身体を動かすことが出来れば必然とパフォーマンスは向上します.
つまり,
- 基本的なスポーツ動作の良いフォームはほとんどの人がイメージできる
- 必要なのは,【自分が思い描くイメージの通りに自分の身体を動かせる事】
詳細なイメージの重要性は??
良いフォームをイメージ出来ると言いましたが,どこまで詳細にイメージ出来るかは少し変わってきます.
‘イメージ通り’ には,全体的なイメージ,『マクロ』な問題と,
もっと細部に注目した『マイクロ』な問題があります.
マクロな問題は『フォーム全体を通してみたとき』のイメージ で,マイクロな問題は『フォームにおけるごく一部分』のイメージです.


例としてバッティングの写真ですが,全体像のマクロなイメージは良いフォームが分かると思います.
しかし,インパクトの瞬間の ‘手の向き’ であったり,‘肘の曲がっている角度’ や,その瞬間にどのような ‘方向に手首が動いていくか’ などの細かい部分はイメージが難しいです.
スポーツのパフォーマンスを追求するにあたっては,この細部をイメージして再現する事も必要になります.
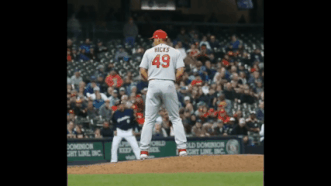

ピッチング動作でも同様です.全体的な投球フォームについてはほとんどイメージ通りかと思います.
上のHicks選手の投球フォームを観て【違和感】が無ければほとんどイメージ通りという事です.
しかし,ボールが指から離れる瞬間 ’リリース’ではどうでしょう?
上の絵のように指先から少しずつ離れていくイメージを持っている人が多いはずです.
画は某有名野球マンガ,【タ〇チ】をアニメ化したエンディングの1カットです.
(オープニングだと思っていましたが,エンディングでした.記憶は結構あいまいですね...)
このカットを観てかどうかは分かりませんが,私たち世代のボールリリースのイメージはコレになっているかと思います.
本来ボールリリースは,上下の指で【つぶす】もしくは【弾く】イメージです.なので,ボールが上下の指から抜けていくのが正しい動きになります.
一例ですが,知らない動作は出来ないので,【マイクロ】なイメージを知っているかどうかも必要だという事がわかります.

イメージ通りに身体を動かすためには!?
良いイメージは出来るけど,その通りに身体を動かすために,【運動学習】という概念を説明します.
勉強のように学術的な学習と同様,運動も反復などにより【動きの質】も良くなります.
この事を【運動学習】と言います.
スポーツが上達するというのは,この【運動学習】 と関わりがあります.
運動学習の一つの効果として,イメージと実際の運動の誤差が小さくなります.
よりイメージ通りに身体を動かせるようになるという事です.
さらにイメージがより正確なものに改善されます.
この【運動学習】の効果を最大化する事がイメージ通りに身体を動かせる近道ですし,スポーツの上達も早くなります.
イメージとの誤差を修正するのに重要なのは,
- 誤差の量を知る
- 誤差を能動的に知る
- 反復する
事です.
運動の誤差の量を知る
『誤差の量を知る』 とは具体的に言うと,
自分の動きと自分が最適と思うイメージとの差がどれくらいかを理解する事です.
どのように実際動いているかを知らなければ,自身が考えるイメージとの差も分かりません.
自分自身の動きがどうなっているかを知るのに一番簡便なのは,鏡です!
たいてい運動する場所には鏡が設置してあります.
鏡を通して自分の動きをチェックするためのものですね.
但し,鏡を使う方法は簡単であり,即座に確認出来るというメリットがありますが,
運動学習という面では不十分な要素もあります.
ひとつは,鏡越しになると左右が逆になります.
左右逆の動きを頭の中で回転して理解する必要があるため,その分だけ正確なイメージとして反映されません.
同じ動きを真似する課題をしたときに,向かい合わせで行うのと後ろ側から見て行うのでは,
後ろ側から見て真似した方が結果が良くなります.
おおまかな説明ですが,それほど左右逆のイメージは反映されにくいという事です.
さらに,動きの途中【マイクロ】な部分を確認する事は困難です.
実際の投球で考えてみましょう.
ある程度の姿勢や脚のステップなど,ポイントポイントで動作を停止して確認するのはまだわかりやすいですが,ボールリリースの細かな手首の動きや指の動きなどは,鏡で確認しながら行うのはかなり難しいです.
何が良いかと言うと,動画を撮影して確認する方法です.
スマートフォンの普及により動画撮影が随分と簡単になりましたし,スローモーションの撮影も120fpsにもほとんどの機種が対応しています.
120fpsあればほとんどのフォームチェックが出来ます.
当方でもオンラインのフォームチェックは120fps以上での動画をお送り頂くよう推奨しています.
さらに動画撮影は各方向からの撮影が重要です.
向かって取るよりは後方だとか,ドローンなどがあれば上方からの撮影も非常に有益です.
動画を撮影してチェックする事で,自身の動作に対して描いている運動のイメージと,実際の運動のフォームに大きな差がある事に気づきます.
このようにして,イメージと運動の誤差を知る事が出来ます.
運動の誤差を能動的に知る
【次に誤差を能動的に知る】事です.
これは【運動学習】についての研究による物ですが,ある動作をしてどれくらいの誤差があったかの第三者からのフィードバックを,
①動作の都度,毎回する
②動作をして,フィードバックが欲しいと思ったらする
グループで分けたとき,②のグループの方が運動学習の結果が良かったのです.
今の自分の運動がどうだったのかを’考えながら’する事が大事なのでしょう.
運動を反復する
もう一つ【運動学習】に必要なのは,反復です.
これはとにかく繰り返す事で,運動の正確性を改善します.
イメージ通りに身体を動かすと言っても,その動作1回ごとに少しずつ【ズレ】は生じます.
毎回全く同じ運動と言うのは実現しません.
ゴルフに例えます.
「ゴルフはミスをしないスポーツで,スイングに誤差があるといけない」と言われます.
しかし,タイガー・ウッズ選手のスイングを解析したところ,左小指に関連する筋肉の働きが,1スイングごとに違ったそうです.
つまり,スイングごとにほんのわずかにズレは生じていて,(おそらく無意識下に)その誤差を修正しているという事です.
このわずかな無意識下の修正は,気の遠くなるような【動作の反復】が実現させた物でしょう.
また同じ運動での誤差には傾向があります.
その傾向がなく,誤差の量や方向がバラバラである場合は,イメージと実際の運動の誤差が大きいと考えられ運動の反復量が少ないといえるでしょう.

運動が上手になる方法,まとめ
運動やスポーツが上手になるには,
①その動作をイメージ出来る事
②イメージが詳細に正確である事
③イメージ通りに身体を動かせる事
イメージ通りに身体を動かすためには,
①自身の動作とイメージの誤差を知る事
②イメージと誤差を小さくするために動作を反復する事
が必要です.
意識化から無意識下などの習得の問題は他にありますが,まずこの段階を経る必要があります.
一度トライしてみると,今まで出来なかった事やさらにスキルを上げたい動作などのパフォーマンスが変わりますよ!
また単体のスポーツとして考えたときのパフォーマンスの向上は複数のスポーツを経験することも重要と考えています.
その内容については→沢山のスポーツを経験しよう に解説しています
最後に上達の概念が良く説明されている図を載せておきます.
是非参考に!

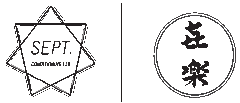
コメントをお書きください
そにつく (金曜日, 25 9月 2020 09:49)
〉〉今の自分の運動がどうだったのかを’考えながら’する事が大事なのでしょう.
以下を見る限り、そういうことではないと自分は考えます
https://www.slideshare.net/mobile/murakamiyusuke/ss-102872471
単純に過剰なフィードバックは、動作の自動化過程では害悪にしかならないと私は上を見て認識しました
恐らくイップスの1原因ではあると考えます
Sept. Conditioning Lab.鈴木 (金曜日, 25 9月 2020 12:57)
そにつく さん
コメントありがとうございます.
フィードバックがあるほど良いとも沢山与えると良いとも考えておりませんし,文中でもそのように解説してあります.
齟齬が生まれている理由をこちらで解釈して返答致しますが,間違った解釈でしたらご容赦ください.
まず,『運動がどうだったかを考えながらする』という事は動作中に思考しながらではなく,あくまで【運動がどうだったか】と言う結果に対して思考するということです.
そして試行者が『フィードバックが欲しい』と判断した時に,フィードバックを与える頻度が運動学習では最も効率的とされています.
内在要素と外在的なフィードバックが共在してしまっていますが,コンテクストとしては外在的なフィードバックを求めるための思考です.
但し運動学習には段階があります.初心者と熟練者では方略も違います.
また運動中の内省的な意識は運動学習やKP,KRを求める上では必要な学習段階もありますので,一概に絶対悪とも言えません.
さらに運動学習の冗長性とでも言いましょうか,一言に【運動学習】と言ってもその内容は様々で,例えば参考資料におけるブラインドタッチの件において,『視覚のフィードバックを抑制することが大事』とされていますが,元々,手指は視覚のフィードバックを頼らず,手指の皮膚や深部感覚を頼りに運動が成立していると言うバックボーンがありますので,『視覚のフィードバックを抑制する』方が良い結果になる訳です.
課題の内容が変われば,自ずと必要なフィードバックの質や量も変化するのでブラインドタッチを引き合いに運動学習を説明すると間違った解釈が生まれます.
上述したように,施行者の熟練度でも運動学習の方略は違いますし,課題によっても適切なフィードバックは変わる訳です.
過剰なフィードバックはもちろん悪しき方に働くでしょう.
しかし過少なフィードバックも運動学習では非効率的であると言えます.
イップスについては依然解明されていない部分も多いですが,単純なフィードバックの量よりもその与える内容や態度による物やそれに付随した経験も大きいでしょう.
フィードバックの授受に力の差があったり,与える側の共有されないイメージだけで伝えたりと言う事があれば,頻度を含めた量とは別の問題があります.
フィードバックについては,【適量】を【的確】に【適切なタイミング】で授受する事が基本でありますが,課題の内容や難易度,施行者の熟練度などによって全く違うのために吟味が必要です.